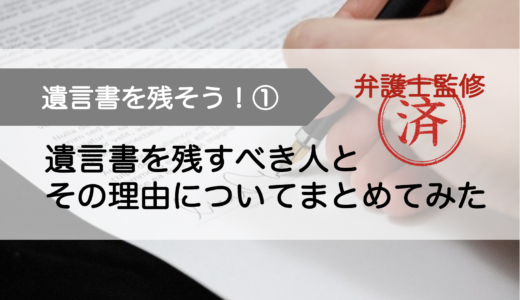- 特定受益とは一部の相続人に対して行った生前の金銭的援助
- 特定受益相当額をプラスしたみなし財産が遺産分割の対象になる
- 遺言書作成により特別受益の持戻し免除が可能
- 特定受益の判断は難しいため弁護士サポートを受けることが望ましい
相続とは亡くなった方の財産を家族や親族、もしくは第三者に譲渡するものですが、その財産は死亡時の資産だけが対象になるのではありません。
故人が生前に金銭的援助をしていた場合は、その相当額が特定受益として扱われることがあります。
はたして特定受益とは何でしょうか。相続人に指定された方が全員納得して円満に相続完了するにはどうしたら良いのでしょうか。
今回は特定受益とは何かについて解説します。
そもそも特別受益とは

特別受益とは、誰かが「特別に」財産を「受けて」得た「利益」のことです。
相続では、故人の保有財産は特に遺言書がない限り、法律で定められた割合で振り分けられます。
しかし特定の人物が生前贈与などを受けていると財産が目減りしてしまい、その状態で振り分けたのでは他の相続人の不利益につながります。
そこで相続人の一部に譲られた生前贈与等を計算し、その分はすでに相続されたものと判断することが特別受益の考え方です。
特別受益の持戻しとは
上記の特別受益が相続人の誰かに発生していた場合は、遺産分割の際に特別受益分をプラスした額を「みなし財産」とし、みなし財産を相続の対象とします。
これを特別受益の持戻しと言います。
特別受益の持戻しの免除とは
特別受益はすべての相続人が公平に遺産を分けられるようにするための制度ですが、状況によっては必ずしも公平が正しい選択とは限りません。
相続人のうちの誰かに財産を集中させるのが被相続人にとって望ましいケースもあります。
そのようなときには遺言書に「特別受益分の譲渡は計算に含まない」旨を書き残せば、特別受益分を相続財産にプラスせずにすみます。
これを特別受益の持戻しの免除と言います。
特別受益の対象になる贈与

特別受益の対象になるのは生前贈与として譲渡した金銭だけではありません。
実際に特別受益に該当するかの判断は個々のケースにより違ってきますが、一般的には以下のような援助も特別受益に値すると考えられています。
生活費
親と同居して生活の面倒を見てもらっていた方は、生活費相当分が特別受益だと他の相続人から主張される場合もあります。
扶養範囲内の生活費であれば特別受益にはあたりませんが、扶養範囲を大きく超えるような生活費の援助は同居・別居に関わらず問題視されるようです。
教育費
兄弟姉妹の中で1人だけ大学に行ったなど、子供同士でかかった教育費が極端に不公平な場合には、学費等も特別受益に該当する可能性があります。
しかし実際に教育費が特別受益として認められるかどうかは、親の資産や社会的地位にも関係してくるためケースバイケースです。
なお、子供ではなく孫の大学進学費用として金銭援助したものは、被相続人の孫は基本的には法定相続人にならないために特別受益の対象外です。
ただし、代襲相続により孫が相続人になったときや、孫への教育援助の名目でも実質的には子世帯への生活援助だったときには特別受益に該当します。
不動産

相続人が所有していた不動産を譲渡された場合にはもちろん特別受益の対象ですが、それだけではなく、その物件を無償で借りて住んでいた場合にも特別受益になる可能性があります。
これは被相続人が本来得られるはずだった家賃相当分を逸失利益として考えるためです。
ただし、これが問題視されるのは被相続人が賃貸経営していたなどの限られたケースであり、普通の住居占有は特別受益と見なさないのが一般的です。
遺贈など
被相続人が遺言書で指定した集中的な相続や遺贈も特別受益の検討対象になります。
ただし、遺言書による特定の相続や遺贈の場合には、特別受益の持戻しの免除に関してもあわせて書かれているケースが多いです。
遺贈と相続の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。
特別受益の計算方法
特別受益の計算は以下のように行います。
(みなし財産の算定)
・相続開始時の財産+特別受益=みなし財産
(みなし財産を各相続人に分配)
・特別受益を受けた方→みなし相続財産×法定割合-特別受益相当額
・特別受益を受けていない方→みなし相続財産×法定割合
計算の具体例
被相続人の相続開始時の財産3,000万円を配偶者および長男(特定受益1,000万円)、次男(特定受益なし)に相続した場合
(みなし財産の算定)
相続開始時の財産3,000万円+特別受益1,000万円=4,000万円
| 相続人 | 計算方法 | 最終的な相続額 |
| 配偶者 | 4,000万円×法定割合1/2 | 2,000万円 |
| 長男 | 4,000万円×法定割合1/4-1,000万円 | 0円 |
| 次男 | 4,000万円×法定割合1/4 | 1,000万円 |
特別特定受益を請求する流れ
被相続人から生前贈与等の援助を受けてこなかった側が特定受益を請求する場合にはどうしたら良いのでしょうか。
特定受益の存在を主張すべきは遺産分割協議をする席上です。いったん遺産分割協議が完了してしまうと、その後の主張はかなり難しくなります。
なお、被相続人が遺言書により特定受益の持戻しの免除を指示していた場合には、特定受益の持戻しの請求はできません。
免除により遺留分が侵害されていると見なされる場合のみ遺留分侵害請求が行えます。
相続法改正により特別受益にも変化が
2019年に施行された改正後の相続法では、特別受益についても変更されています。
以下では相続法改正により特定受益の扱いが変化した箇所のみご説明します。特定受益以外の変更点については以下の記事をご覧ください。
特定受益の持戻し対象期間
改正前の相続法では特別受益の期間に制限は設けられていませんでしたが、改正後の相続法では特別受益の持ち戻し対象となる贈与期間が10年間に制限されました。
第7章 遺言
第4節 遺言の執行
第1044条3項(遺留分を算定するための財産の価額)相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
引用:e-Gov法令検索|民法
配偶者への持ち戻し免除の推定
婚姻期間が20年以上の夫婦で、夫または妻が配偶者に自宅を贈与した場合には遺言書の有無に関係なく特定受益から除外されることになりました。
これを特別受益の持戻し免除の意思表示の推定と言います。
第7章 遺言
第2節 相続分
第903条4項(特別受益者の相続分)婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
引用:e-Gov法令検索|民法
特別受益のトラブルは遺言書で解決

遺産を譲る立場としては、たとえ自分の死後でも家族間のトラブルは避けたいものです。
特別受益に該当しそうな援助をした覚えがある方は、必ず遺言書を書いておきましょう。
特別受益の持ち戻しの免除を指示できるのは遺言書だけですし、逆に、譲渡済の援助をみなし財産に算入させて相続人間の公平を図ることもできます。
特別受益をどう扱うかは相続人の自由ですが、大切な家族にいさかいが起きないように対処するのは被相続人の責務です。
特別受益の扱い以外にも、遺言書を書いておいた方が望ましいケースはいくつかあります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
弁護士サポートを受けると安心
生前の譲渡や援助が特別受益に該当するかどうかは状況により異なるため、素人判断は非常に危険です。
不用意に特別受益について言及したり、また言及しなかったりすることで相続人同士のトラブルを招く可能性もあります。
また、遺言書の作成自体も、法律にのっとった文書でなければ無効になります。
遺言書で特別受益に関する指示をしたい方は、特別受益の判例に詳しい弁護士のサポートを受けながら作成することをおすすめします。
まとめ

今回は特別受益について解説しました。
特別受益とは相続に際して、被相続人の生前のふるまいを総決算する重要な制度です。
援助をした方も、援助を受けた方も、そして援助を受けなかった方も、そのすべてが円満に相続できるように生前からの対策をしっかり行いましょう。