- 終活カウンセラーは終活の総合的な知識が身につく資格
- 2級は自分の終活ができるのが目標
- 1級は他人の終活のお手伝いができるのが目標
最近は「終活」という言葉も浸透し、元気なうちからエンディングノートを作ったり身の回りを整理したりする方も増えています。ただ、なかには「終活って何をして良いか分からない……」と悩んでいる方もいるでしょう。
終活の進め方が分からない方は、資格取得を通じて知識を身につけることがおすすめです。自分の終活はもちろん、知識を深めれば家族や友人の相談に乗ることも可能です。
今回は終活に関する資格である「終活カウンセラー」について、資格の特徴と身につく知識を解説します。
目次
終活カウンセラーとは

終活カウンセラーは、「終活」に関して「カウンセラー」として話を聴けるスキルを持った有資格者のことです。
最近は葬儀や高齢者向けサービスが多く、どこを選べばいいのかわからない方も増えています。そんな方の悩みを聞いて、適切にアドバイスができることを目指す資格です。
葬儀・相続・介護など終活の知識を問われる民間資格
一般社団法人終活カウンセラー協会が設けている民間資格です。
終活に関する業務を行うのは国家資格を持つ「弁護士」「司法書士」「行政書士」「FP技能士」などを持つ専門家で、終活カウンセラーの資格だけで独立開業できるわけではありません。
終活カウンセラーのメリットは、自分が終活の知識を身につけることで、自分はもちろん、親や友人の役に立てることです。
終活カウンセラーは2級・1級・認定講師と3つのクラスに分かれていて、2級は自分のために知識を身につけることを目標にしています。一般的な終活の知識を身につけることで、自分の残りの人生を見つめ直すキッカケになるでしょう。
専門家への橋渡し役にも
終活カウンセラーとして、ほかの専門家への橋渡し役になることも終活カウンセラーの役割です。
- 相続における親族間のトラブル:弁護士
- 相続に関する税金の悩み:税理士
- 相続した不動産の登記に関する悩み:司法書士
- 相続に関する書類の手続き:行政書士
- 余生のお金に関する相談:ファイナンシャルプランナー
- 葬儀の悩み:葬祭ディレクター
- 保険の悩み:保険会社
士業などの各専門家にはそれぞれ独占業務・得意分野があります。資格取得を通じて終活の流れを理解できれば、専門家への橋渡し役になれるでしょう。
士業の専門家のブランディングにも利用できる
終活カウンセラー認定資格は、学習を通じて幅広い知識を身につけられます。
- 相続
- 遺言
- 保険
- 葬儀
- 介護 など
一般人のほかに、保険会社や士業など終活の相談を受ける立場にある方にも有効です。終活カウンセラーというブランドの認知度が高まることで「終活に強い人」というアピールができ、競合との差別化に利用できます。
終活カウンセラーの年収・給与
終活カウンセラーの資格だけで独立・開業することは難しいです。大半の方は本業をしながら必要に迫られて取得します。
本業の年収・給与が、そのまま終活カウンセラーの年収として考えられます。一概に「終活カウンセラーの年収は●円」と断言はできません。
ただ、士業などの専門家が終活カウンセラーを取得して終活に強いことをアピールすれば、結果的に集客力アップ(=収入増)につながることもあります。
終活カウンセラーの資格を得るための試験内容

終活カウンセラーは国家資格のように「落とすための試験」ではありませんが、それでも一定の条件を満たさないと取得できません。
ここでは最初に受けることになる2級を参考に、試験の流れを解説します。
2級試験の流れ
終活カウンセラーの資格は、1級と2級に分かれています。2級は「自分の終活ができるレベルの知識」「家族や友人に訪ねられたときに対応できる知識」を問われます。
試験の流れは以下のとおりです。
- 約6時間の講習を受講する
- 講習が終わったあとに筆記試験を受講する
- 試験に合格したあと、2級終活カウンセラーに認定
受講申し込み後に受講料を支払うと、終活カウンセラー2級のテキストが送付されます。
試験当日まではテキストと付属の練習問題を使って勉強し、試験本番はテキストの解説を受けたあとで試験に臨む形式です。
現在は通信教育講座も開講されています。Zoomを使ったオンライン検定が可能で、自宅や職場にいながら資格取得にチャレンジできます。
試験問題
試験の際は約6時間の講義(昼休憩付き)を行います。試験時間は最後の30分間です。
受講料
2級の受講料は15,000円(税込)です。
この受講料には講習代・試験代のほか、当日にもらえるお弁当も含まれます。オンライン検定を選択した場合、お弁当の代わりにエンディングノートが1冊プレゼントされます。
試験の難易度
終活カウンセラーの合格率は非公表です。ただ、以前は合格率が公表されていました。そのときの2級相当の資格の合格率は95%を超えています。
昼休憩を挟んで6時間の講義を受けてからの試験になるので、知識がない状態で臨んでも合格できる体制が整えられています。
2級に関しては「自分のために知識を付ける」ことが目的ですし、気軽に受験できるレベルといえるでしょう。
2級認定者は1級終活カウンセラーも目指せる

2級に認定された方が更なる知識を身につけたい場合、1級カウンセラーを選ぶ道もあります。
エンディングノートの書き方を指導できる
1級カウンセラーでは、自分以外の方の終活に対応できる知識が求められます。
他の方のエンディングノート作成をサポートすることが目標です。終活の知識を使って、他の方とのコミュニケーションを起こす力を身につけることも求められます。
士業などの終活のスペシャリストなら、1級の取得を目指しましょう。実務のなかでエンディングノート作成のアドバイスやサポートができれば、競合との差別点として活用できます。
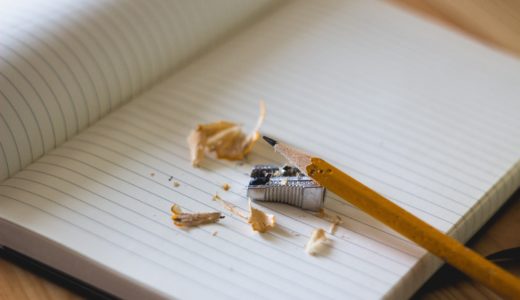 エンディングノートにおける「基本情報」の書き方
エンディングノートにおける「基本情報」の書き方
取得の条件は2級より厳しめ
1級カウンセラーを目指す場合、取得の難易度は高まります。2級を持っていることが前提なだけでなく、取得までに以下のようなハードルがあります。
- 事前レポート提出
- 試験込みで2日間の講習
- 協会主催の勉強会に年1回参加 など
自分の終活に関する知識を得たいだけならここまで受けずとも、2級までの知識で十分です。1級を受ける場合は、その知識を使う場面が来るかを想定しておくことをおすすめします。
終活カウンセラーと終活アドバイザーとの違い

終活カウンセラーとは違う資格で、NPO法人ら・し・さ認定の終活アドバイザーという資格もあります。
終活アドバイザーは「エンディングノートのアドバイスができる」「終活に困る人の相談相手になる」ことを目指した資格です。基本的に終活カウンセラーと似た知識を問われます。
生涯学習のユーキャンが終活アドバイザー試験に対応していて、通信教育により自宅で取得することが可能です。受講後に修了試験を受験して合格すれば、終活アドバイザー資格者になれます。
「終活カウンセラーとどっちを受けたほうが良いの?」と悩んだときは、それぞれの資格の特徴から自分に合ったものを選択しましょう。両者を比較してみると、以下の点が異なります。
資格取得にかかる費用
終活カウンセラーと終活アドバイザーにかかる費用を比べると、以下のように違いがあります。
- 終活アドバイザー:一括払い35,000円+入会+登録費用 10,000円
- 終活カウンセラー:2級15,000円/1級45,000円(オンライン50,000円)
初めて終活に関する資格を取得する場合、終活カウンセラー2級の方が安く済ませることができます。単純に料金で比較すれば終活カウンセラー2級が狙い目です。ただ、1級まで目指すとなると複数回の費用が発生します。
級分けの有無
終活アドバイザーは級分けがなく、1つ資格を取得すればそこで終わりです。一方の終活カウンセラーは以下のようにランク分けが存在します。
- 2級終活カウンセラー
- 1級終活カウンセラー
- 終活カウンセラー協会認定終活講師
2級は自分の終活ができるレベル、1級は人の終活をサポートできるレベル、認定講師は更に上のレベルといった具合に難易度が分かれており、1級以上を受けるには協会開催の勉強会の参加も必須です。
終活に関してじっくり勉強して知識を得るなら終活カウンセラーがおすすめです。逆に1回の試験で他人にアドバイスできるレベルまで進めたい方は終活アドバイザーが向いています。
会場で講義を受けられるか否か
終活カウンセラーと終活アドバイザーでは、試験の方法が異なります。
- 終活カウンセラー:オンラインまたは会場
- 終活アドバイザー:オンライン
オンラインであれば自宅で気軽に受講できますが、可能であれば会場での受講がおすすめです。やはり講師の講義を生で聞く方が知識として身につきやすいですし、不明点を質問することもできるでしょう。
その点、終活カウンセラーは全国に会場があります。実地で講義を受けたい人は終活カウンセラーがおすすめといえそうです。
まとめ
今回は「終活カウンセラー」について、資格の特徴と身につく知識を解説しました。
終活の内容は多種多様で、いきなり始めようと思っても上手くできないことも多いです。終活カウンセラーは資格の取得を通じて「葬儀」「保険」「介護」などあらゆる分野の知識を身につけるので、自分が終活する際のヒントを得られます。
親や兄弟の終活まで助けてあげたい方は、じっくり勉強して1級以上を目指すのも良いでしょう。

GoldenYearsでは、充実したセカンドライフを送るためのサポートを行っております。
終活カウンセラーやエンドオブライフケアなど専門知識を持ったプロフェッショナルチームへの相談が可能です。少しでもわからないことがあれば、ご気軽に以下お問い合わせフォームよりご連絡ください(無料)。
▶︎お問い合わせフォームへ



